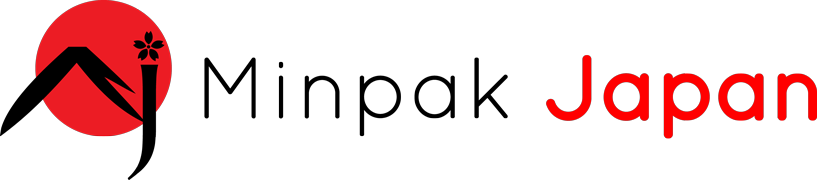もし、あなたがこれから民泊を経営してみたいとお考えなら、こんな不安ございませんか?
「地域住民から苦情や利用者のマナー違反があった場合の対応ってどうすればいいだろう・・・」
最近、民泊のトラブルに関するニュースをよく見るようになりました。このような報道から民泊施設の運営はもう少し検討しようとい方も多いのでないでしょうか。民泊トラブルの一例をご紹介します。
- オーナーに無断で賃貸マンションが民泊として又貸しされるケース
- 居住者以外の不特定多数の出入りによる住民の不安
- 深夜の騒音やルールを無視したゴミの処理など近隣住民から苦情
これらのニュースが増加している背景として、民泊ビジネスに参入する企業や仲介業者の増加により「民泊サービス市場」が急速に成長しているという背景があります。
また、苦情発生時のずさんな対応がトラブル増加を招いているとも考えられます。
民泊サービス トラブルの実態
民泊に関するトラブルは主に次の5つが想定されます。
- 騒音トラブル
- ゴミ問題
- 防犯上のトラブル
- 安全上の問題
- 宿泊客とのトラブル
騒音やゴミの問題などは、サービス利用時際、宿泊者に明確に伝えないといけない注意事項です。防犯上のトラブルや、安全上の問題については、地域住民に事前の告知と説明、運営者の緊急連絡先の開示など近隣への配慮と対応が不可欠です。
急に不特定多数の外国人が出入りし始めることによるセキュリティー面への不安感や、騒音やごみなどの苦情を伝えることができないなど、民泊サービスを快く思っていない地域住民も存在します。
民泊サービスを始めるにあたり、あらかじめトラブルを想定しておくことは、民泊ビジネスを運営するのに重要な要素の一つです。ここでは、民泊の実態調査、地域住民の意識調査をもとに民泊に関するトラブルを解説していきます。
地域住民の意識と全体の傾向
「京都市民泊施設実態調査」によると、施設周辺の住民に対するヒアリングしたところ、開業の告知もなく、管理者の連絡先や宿泊施設であるいう表示がないことによる不安感やトラブルが発生していることがわかります。
引用元: 京都市民泊施設実態調査:
- 施設周辺の住民は民泊施設の開業に当たっての事前説明をされていない。
- 管理者が常駐せず,誰がどのように運営をしているか分からない,また,トラブル時の連絡先も分からないことなどが,周辺の住人の不安を更に増大させている。
- 外観からは宿泊施設であるかどうか判別はできず,宿泊客が迷うケースもある。
- 施設が周辺住民に及ぼす影響は,周辺の住民の生活様式等によっても大きく異なってくる。
- 施設が周辺住民に及ぼす影響は,運営者の管理能力によるところが大きい。
騒音問題・事前告知不足・セキュリティー問題
もし、あなたの自宅マンションに訪日外国人が出入りを始めたらどんな印象をもちますか?
事前の告知もなく、民泊サービスが始まり、深夜の雑音が止むことがない。少し想像するだけでも、不安になりますよね。
京都市民泊施設実態調査では、戸建と集合住宅を対象に民泊に関する地域住民への聞き込み調査をしています。
戸建て住宅における傾向
戸建て住宅の場合、多くの来日外国人が宿泊可能なため、騒音につながりやすいようです。人数が増えれば、雑談の声も大きくなります。またパーティーなどが開催されればお酒が入ることでさらに大きな騒音がでることも予想されます。
集合住宅の施設と比較して,多くの人数が宿泊可能なため,騒音につながりやすい。 特に連棟になっている場合や路地奥にある施設における騒音は深刻であり,宿泊者のいびきで眠れないというケースもある。 また,路地奥での施設については火災の心配の声が多く聞かれた。 運営者からの説明や問い合わせ先の開示を受けていない場合は,トラブル時に苦情を伝える先がないため,宿泊客本人に直接訴えるか,警察に通報するかしか手段がない。 引用元: 京都市民泊施設実態調査:
集合住宅における傾向
集合住宅の場合でも、多数の民泊が運営されている場合、深夜にインターホンを間違って鳴らさたり、マンション共有部分で雑談するなどの行為も発生するそうです。
不特定多数の観光客が宿泊することで,オートロックの意味がなくなっていることに多くの住人が不安を感じている。 ごみや騒音などの具体的な迷惑行為があるという声は多くはなかった。 しかしながら,1つの集合住宅で多数の民泊が運営されている物件においては,ごみ問題,騒音,深夜にインターホンを間違って鳴らされたなどの具体的な迷惑を被っているという声もあり,物件からの退去を考えているという住人もいる。 一方で,単身世帯用の物件であれば,住人が民泊施設に気づいていないケースも見られる。また,大型の単身世帯用物件になればその傾向は更に強まる。 集合住宅の住人が苦情を訴えても,対応しない不動産管理会社もある。 引用元: 京都市民泊施設実態調査:
地域住民へ事前告知
前述の「京都市民泊施設実態調査」に内容をを踏まえ、これから民泊をスタートするには、次の3点に注意することをおすすめします。
- 「民泊」を開始したい旨を近隣住民に説明を行い、事前に理解を求めておくこと
- 騒音やごみの問題に対して、近隣住民の理解を得るための措置を講じること
- 利用者と近隣住民向けに宿泊施設の看板(管理人の連絡先など)を設置すること
上記3つは、今後の法律改正や民泊新法の成立により義務化される可能性があります。
民泊サービスに対する地域住民の意識調査
2016年2月に実施された株式会社ジャストシステムによるネットリサーチによると、民泊サービスが犯罪目的で利用されること不安視していることがわかりました。民泊がトラブルにつながるという意識を持っている方が多いようです。
民泊を知っている人に、民泊サービスの自由化について質問したところ、「トラブルを未然に防ぐための『法整備』をするならば賛成してもいい」が最も多く、「民泊サービスの自由化を歓迎する」と回答した人は7.7%でした。
「Airbnb(エアビーアンドビー)」の認知率は約40%アメリカ発祥の「民泊サービス」である「Airbnb(エアビーアンドビー)」について、「知っていて、その内容を他の人に説明できる」人は15.9%、「知っているが、その内容までは詳しく説明できない」人は24.3%で、合計すると40.2%の人が認知していました。また、「民泊」という言葉は90.1%の人が知っており、言葉自体は既に人々のなかに広く浸透しているようです。
約7割が犯罪目的で利用されることを不安視「民泊」認知者のうち、「民泊サービス」が犯罪目的で利用される可能性について、66.7%の人が不安に感じていることがわかりました。 ※「あてはまる」「ややあてはまる」の合計。
戸建て居住者の約3割が、周辺で「民泊サービス」が増えたら「引っ越し」を検討戸建て住宅(持ち家)に住んでいる「民泊」認知者のうち、自宅の周辺で「民泊サービス」が増えたら、27.9%の人が引っ越しを検討すると回答しました。※「あてはまる」「ややあてはまる」の合計。
半数以上が「民泊サービスは現行法に抵触」する可能性を認知「民泊」認知者のうち、「民泊サービスが旅館業法などの現行法に抵触」する可能性があることを、「知っていて、他の人にも説明できる」人は20.3%、「知っているが、他の人に説明することはできない」人は32.0%でした。合計すると52.3%と、半数以上の人が現行法に抵触する可能性を認識していました。
4割近くが民泊サービスの自由化に「反対」。歓迎派はわずか7.7%「民泊」認知者に「民泊サービスが解禁になる」という報道について意見を聞いたところ、「トラブルを未然に防ぐための『法整備』をするならば賛成してもいい」が最も多く(46.2%)、次いで「犯罪などの温床になる可能性があるので、どちらかといえば反対」(26.1%)、「民泊サービスの自由化には絶対反対」(11.3%)でした。一方、「民泊サービスの自由化を歓迎する」と回答した人は7.7%でした。
引用元: 戸建て居住者の3割が、周辺で「民泊」が増えたら、「引っ越し」を検討 都民の関心高し!「民泊」に関する意識調査
現時点では、民泊を積極的に地域に受け入れても良いという意見は少ないことが伺えます。法整備により、民泊サービスのあり方が明確になれば、この傾向は変わるかもしれません。
まとめ
政府の規制改革会議がまとめた「規制改革に関する第4次答申」によると「近隣トラブル防止」を重視しており、民泊利用者に事前の注意喚起(騒音やゴミ処理など)を行うことや、近隣住民からの苦情対応を適切に行うことを義務付ける方針を出しています。
また、民泊サービスをインターネット上で仲介する場合、住居物件が民泊施設であることをインターネット上で告知しなければならず施設周辺の住民への配慮を意識した方針が盛り込まれています。
トラブル、苦情対策、地域住民の皆様への配慮を心がければ、品質の高い民泊サービスを運営できるはずです。